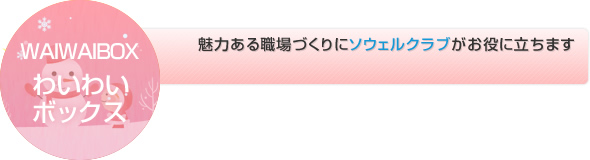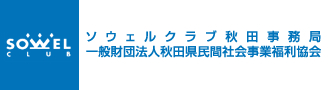良い変化に目を向けて

<安藤亘の1分間カウンセリング 7年1月>
Q.障害者支援施設で事務(総務関係)の仕事をしています。家庭は私、妻、長男、長女、次女の5人家族で、現在妻は同じ業界で介護職として忙しく仕事をしていて不規則勤務のため、主に定時で仕事が終わる私が家の炊事洗濯等家事全般を行うのが日課です。相談は私自身のお酒のことについて。私は学生時代からお酒が好きで、社会人になってもその習慣は変わらず。酒の席では自分のテンションが上がり、楽しいお酒でした。最近は仕事を終え自宅に帰って夕飯の支度をする際、お酒を入れないと気持ちが上がらずそのままエスカレートして、ついグイグイいってしまいます。翌日お酒が残ったり、家族に怒鳴ったりするようになってきたので、思い切って断酒しようとしました。しかし、不眠、焦り、不安感等が生じて再飲酒してしまいます。この悪循環を何とかしたいのですが…
(S治:53歳)
A.S治さん、相談内容をお伺いして率直にまず“生き方”に無理があるな、と感じました。
「お酒」は別の言い方をすると“脳全体に作用する質の悪い向精神薬”。身体的、精神的依存性がかなり強く、慢性化・習慣化しやすいため(飲酒歴が長く習慣化している方の場合)、飲酒を急にやめようとすると離脱症状(不安・焦燥感、発汗、不眠等)が生じ、その苦しさから再飲酒してしまうケースが多いのです。
まずは飲酒することによるメリット・デメリット、断酒(禁酒)することによるメリット・デメリットを明確にします。そのうえで、断酒された際のメリットに意識を向け、それを励みに何とか断酒を継続され、離脱症状を乗り切ってください。
長期の休み(ゴールデンウィークや夏休み、年末年始等)の際に、周囲の家族の理解を得つつトライされるのが良いでしょう。始めは不安感やイライラ、孤立感等に苦しむことでしょう。しかし、それは想定内のこと。3日ほどすると肌の調子が良くなる、胃腸の不具合が改善する等メリットが生じてきます。
まずは2週間。睡眠の質が良くなってきて、さらに苦しい飲酒欲求がかなり軽減され、良いサイクルが回り始めます。
S治さんはアルコールのご相談でしたが、精神科で「適応障害」や「抑うつ状態」「うつ病」等と診断され、処方される抗不安剤や睡眠導入剤も身体的・精神的依存症が高いものが多く、急に減らしたりやめたりすると、やはり離脱症状(不安・焦燥感、発汗、不眠等)が生じて、結果なかなか薬が手放せなくなってしまいます。受診されていて主治医がいる方の場合は主治医に相談しつつ、計画的に少しずつ時間をかけて減らしていくことが大切です。
心の問題は、目に見えませんし波があるのが普通です。調子良いな、と思っても、急に落ち込んだり不調になったりします。
“そういうものだ”“何とかなるさ”“想定内のこと”と気持ちを切り替えつつ、ひと呼吸おきながら断酒による自分の良い変化に意識を向けましょう。ひとりでは難しい場合は、専門機関のドアを叩き、専門家の協力を得ながら乗り切ってくださいね。
自分の身を亡ぼす良くない依存対象から、健全な依存対象が増えてきた時、本当のS治さんらしさが取り戻せます。
自分を大切に。応援しています。