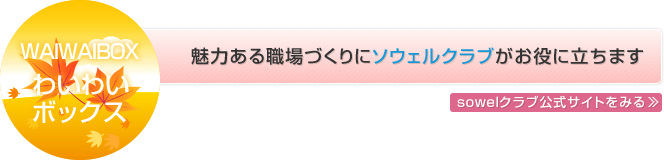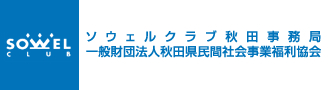1.5人関係??

<安藤亘の1分間カウンセリング 6年11月>
Q.私は高齢者入所施設に介護職員(常勤)として働いています。直接仕事のことでないのですが、最近の私の悩みの種、それは子どものこと。上が高1(長男:16歳)、下が中2(長女:14歳)で、ふたりとも思春期ど真ん中。私自身忙しく仕事してきましたが意識して子どもとは会話をたくさんしてきたつもりです。でも最近は「今日学校、どんなだった?」と聞いても「普通〜」と。スマホで友達とのやり取り以外にも漫画を読んだりゲームをしたり。その時間が結構長い!私も遅くまで起きていますが、子どももゴソゴソ音がするのでおそらく夜遅くまでスマホやゲーム、友達とやり取りして起きているようで、このままで良いのか悩みどころです。
(Q香:45歳)
A.Q香さん、以前のように子どもが何でも話してくれるわけでもなくコミュニケーションの量が減るとどうしてもネガティブな方向(心配事)へと意識が向かいますよね。
年ごろ(特に思春期)の子どものいる家庭では、かなり多くの親御さんがQ香さんのような悩みを抱えていらっしゃると思います。
子どものゲームやスマホとの付き合い方も気になるところでしょう。生身の人間とのやり取りが「2人関係」。ゲームやスマホ、インターネットは子どもにとって「1.5人関係」。アルコールや薬物も1.5人関係。つまり、一方的な(傷つくことのない)関係のことです。
そのため、付き合い方が難しい。過度に依存すると、他のことが手につかなくなり、そのため親が取り上げたり制限したりしようとすると対立をもたらします。子どもに徐々に学んでもらうのは、その「付き合い方」でしょう。
ちなみに親であるQ香さんは家でスマホをどれくらい使っているでしょうか。「何で大人は良くて子どもはダメなのか」と詰め寄る子どももいるくらいですから、親もスマホとの付き合い方や子どもから問われた時への「返し」は用意しておいた方がよいかもしれません。
スマホとの付き合い方は、まずは親自身。「本当に必要か」「何のために使うのか」を意識していきましょう。
少し話は飛躍しますが、人間は明るくなったら起き、朝ご飯を食べ、太陽の光を浴びて活動し、暗くなったら寝るようにできています。つまり心身の健康を維持・向上していくために必要なのは生活リズムです。
その大敵がスマホやゲーム、インターネット。夜間のブルーライトは脳を覚醒させ、睡眠の質を下げることが知られています。
人間の身体の中の構造は、原始の時代(森の中、木の上で暮らしていた時)とほとんど変わっていないそうです。つまり、暗くなってもいつまでも起きていて良いようにはできていないということです。
さて、科学の進歩は目に見張るものがあります。ただ、長所短所は表裏一体。原発がそうですね。新しい技術を生活に取り入れるためには、その「長所」と「短所」を明確に意識し、長所が活きる場面にだけ使う。短所は最小限に。スマホでいえば、夜10時以降は「交感(張りの)神経」から「副交感(緩みの)神経」へと切り替わる、つまり身体の緊張を緩めて疲れを癒す神経が優位になる大事な時間帯です。
子育ては、親が年を重ねていくにつれて、子どもが親に与えるストレスも変化していきます。始めは肉体的ストレスが中心ですが、思春期以降は精神的ストレスに比重が置かれるように。上手くできていますね。
そして子どもが勝手に成長していくわけではありません。親も悩み苦しみ、悶えながら成長していかないと、子どもは成長していきません。
子育ては、子どもの可能性を信じることができるかどうか。それには「放任」ではなく、「見守り待つ」。
子育てを楽しみながら、まずは親であるQ香さん自身が生活リズムを整えてくださいね。応援しております!