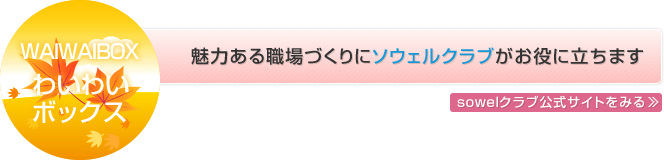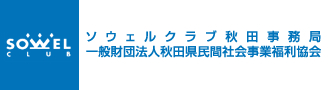裏のコミュニケーションとなる前に…

<安藤亘の1分間カウンセリング 6年9月>
Q.保育の専門学校を卒業し、地元の民間中規模の保育園(職員数:20名)に就職。園庭が狭く、年中・年長さんは毎日外の公園へ。戦後の青空保育の頃からある“どろんこ保育”です。大ベテランの層が厚く、若い人は少ない。プレッシャーもあるので会議の席では意見が言えない雰囲気があります。勇気を出して発言しても結局経験が長い保育士の意見が通ることが多く、結果若手は会議ではほとんど発言しなくなりました。園を利用する親はもう世代交代していて、清潔で綺麗な保育園を望んでいるのに… いつもがちゃがちゃ、手づくりおもちゃは古く、イベントやお泊り保育も多く若い職員は疲弊しています。
(O美:25歳)
A.O美さん、ご相談ありがとうございます。保育園の若手職員からよく寄せられる悩み(事案)です。とはいえ、保育園はそれぞれ歴史も違いますし、人の悩みはそれぞれですよね。
保育に限らず、ひとりで完結する仕事はひとつもありません。つまり、職員同士が上手く連携を図って何とかしていく。そのために必要なものは何でしょう?
今の状況が続くとコミュニケーションが表でなく裏(悪口、噂話等々ネガティブコミュニケーション)になってしまいます。
視点を変えて、経験の長い先輩保育士からすると、若手に対して意見を言わない、消極的だとみえると思います。
状況に応じて立場や視点が違うと、捉え方は全く異なるものになります。
まずは自分(O美さん)から変えていきませんか。それができないからここに相談したと叱られてしまうかもしれませんが…。
会議で意見を言わないと、100%丸呑み(賛同)したのと同じこと。勇気をもって必ず意見するようにしましょう。自分自身にシンプルなルールをつくるのです。
気になることがあったら、お腹にため込まない。そうすることが自分や組織、仕事(保育:子ども)に良い影響を及ぼす(主体的に仕事に向き合い、職場に居場所をつくっていく)ことに直接つながっていきます。
「受身から主体へ」「今、自分にできることは何なのか」「ピンチをチャンスに変えよう」それがキーワードであり、働く人の職責(職務における責務)なのではないでしょうか。
O美さんが一歩踏み出すことは、O美さんが“自分やご家族、周りの人たちを幸せにすること”に直接つながっていきます。
陰ながら応援しております。