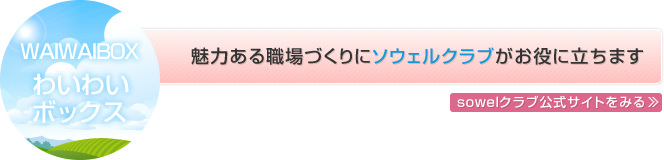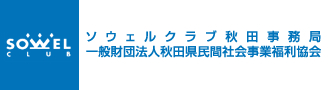対象は変われど…

<安藤 亘の1分間カウンセリング 4年6月>
Q.保育園や高齢者の入所施設、障害者支援施設等を運営する社会福祉法人で保育士として保育の仕事をしてきました。
最近主任となり、上司から管理職として障害者施設への異動もあり得るので社会福祉主事の資格を取得するよう言われました。保育も福祉領域のひとつであるとは思いますが、ずっと子どもと接し育てる仕事でしたので、何となく苦手意識が…
まだ異動が決まったわけではありませんが、どんな心構えでいたらよいでしょうか。
(N美:40歳)
A.そうですね。接するご利用者は子どもから障害者へ変わりますが、今回は変わらない部分(福祉の仕事の本質)をみていきましょう。
まずはご利用者に対して「I am OK/You are OK」であるということ。N美さんが関わる対象が「子ども」であっても「高齢者」であっても「障害者」であっても、人としてお互いに対等(ニュートラル)であるという深い認識です。それを「権利擁護」といいます。どのような支援であってもこの権利擁護を根底に置いた支援でなければすべてむなしいもの(単なる作業)となってしまいます。
次に「支援」は「虐待」と紙一重であるということ。対象が誰であれ、支援者が本人のできることまでしてしまえば「権利侵害」に等しく、その対象の力を奪い、結果できない人にしてしまう危険をはらんでいるということを常に意識して関わる(支援する)ことが大切です。
N美さんは子どもにそのように対応されてこられたのではないでしょうか。それは対象が「高齢者」であろうと「障害者」であろうと同じです。つまり対象は変われど、人に関わる際の根底を流れる価値は共通しているということです。
今回は福祉現場の根底に流れる価値(権利擁護)についてお話しました。最後に、福祉の仕事は変化の連続。日々、必ず「何か」が起こります。人の宿命ですね。起こったことに対処・対応していくしかないのが人間のさだめです。
現場の方は仕事では勿論ご利用者、そのご家族、そしてプライベートでは自分の子どもや配偶者、複雑な人間関係のなかで、結果自分が後回しになりがち。日によって自分の気分や体調は変化しますが、日々力(手)を抜くことができない仕事をされているので、時に自分を優先し、自分にやさしく自分らしく、そして自分にご褒美を。
仕事の帰りがけ、コンビニに寄って好きなスイーツを買って帰る、季節のものを食べる、休日は自分のペースで少しゆっくり散歩してみる等々。
N美さんが幸せになって不幸になる人はひとりもいません。N美さんが今後も擦り切れることなく、日々生きいきとしたよい仕事を展開されること、期待しております。